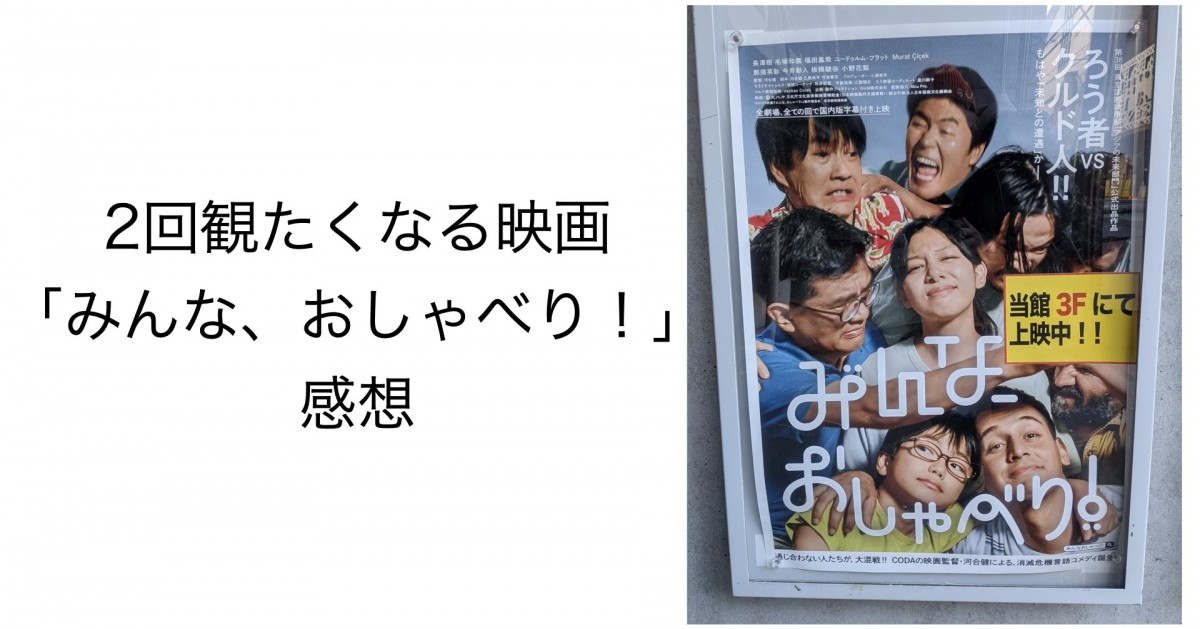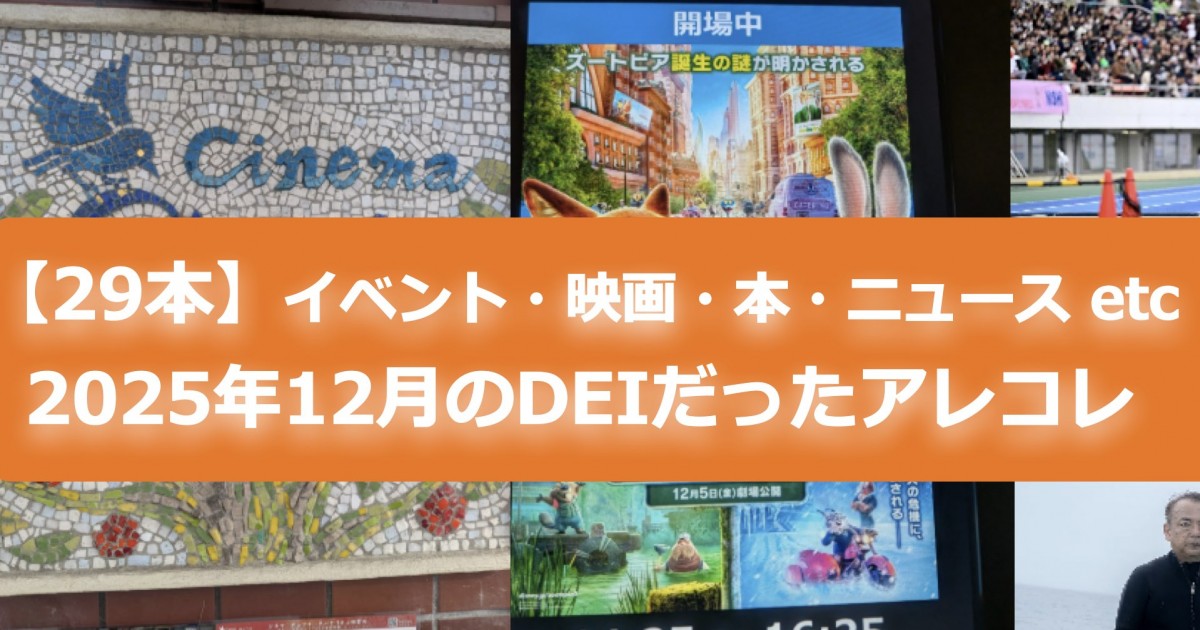婿と姑が編み物で、15年ごしに分かり合えた話
嫁姑問題は、よく聞く。婿姑問題というのは、あるんだろうか。
姑と話していると、途方に暮れる。こんなに分かり合えないものか、と。多様性という言葉を、しみじみ噛み締めてしまうことも多い。もし彼女にこれを聞かれたら「その言葉、そっくりそのままアンタに返しちゃん」と言われるだろうけれど。
そりゃ妻の母親なのだから、年齢、性別、居住地、価値観、何もかもが違う。とはいえ”妻=娘を愛している”という運命的な共通点があるわけで、そこから互いの理解へもう少し進んでも良さそうなものなのだけれど、結婚して早15年、前進どころか後退してそうな気さえする。
私がメンタルで休職することになった時も。
「は〜情けねぇ。アンタそれでも男かぇ。うちのおとんは、九州男児やったけんね。そげつまらんことにならんかった」
「耳は二つあるんで?かたっぽ聴けなくなっても大したことねぇ。難聴なんてしゃあしいわ」
「気合が足りんのよ。しんけんきばりよ。それでだいたいのことはなんとかなるけん」
と、バリバリの大分弁で叱咤激励。マジか。心を病んだ人間にとってそれは凶器、ということを知らない様子だった。愛の無知。うまくない。
挙句、
「アンタがしっかりせんと、結太がそげなことになりよんのや。嫁がピシャっちせな、ピシャーっち。東京なんかにやらんけりゃよかった」
と妻までバッサリ斬る始末。冤罪御免。姑のがなり声で音割れするスマホを、妻はそっとテーブルに置いていた。結婚してからずっと、ことあるごとにこの調子。あーやっぱり、この人のことは、理解できない。
そんな姑に、私が編み物を始めたことが、バレた。
ある晩。私がソファで編み棒を繰っていると、娘の話し声がダイニングから聞こえた。
「パパはいま編み物やってまーす」
目をそちらにやると、娘がタブレットのカメラを私に向けている。ばーば孝行のビデオ通話。話題が尽きて、私の様子を中継することにしたらしい。そりゃ46歳で編み物を始めたお父さんは、格好のネタだろう。
8歳なりのサービス精神は誉めてやりたかったが、それ以上に私は隠れたかった。ひとの無防備なところに土足で、それもスパイクで上がり込んでくる。それが姑。どうせまた女々しいだの都はるみだのと、いつもの小言が始まるに決まっている。私はソファから立ち上がった。
すると。タブレットから、あの大声が聞こえた。
「結っちゃん編み物しよんのかぇ。それはあれやね、輪針やね」
なんで知ってる?輪針とは、編み棒と編み棒をコードでつなげた、編み物界のヌンチャク。
「何編んじょんの?」
私は娘の手からタブレットを受け取り、ダイニングに座り直した。画面の中の姑は、缶チューハイで頬が赤い。
「私も昔はよう編みよったんよ」
彼女は、肴をつまむように語りだした。生まれてすぐ戦争が終わったこと。大分の山村で、物不足がひどかったこと。私の娘の年頃にはもう親を手伝うようになり、お父さんやお兄さんの服を編んでいたこと。結婚してからも習い性が抜けず、夫と三人の子どもたちの靴下や腹巻き、マフラーやセーターを、夜ごと編んできたこと。ひび割れが痛かったん覚えてるわ、と指先をさすりながら笑った。
そういえば、末娘である妻が上京してきた日。引っ越しの段ボールには、手編みの靴下がたくさん入っていた。カラフルな、一足として色が揃っていない毛糸の靴下たちが、品々の隙間に詰め込まれていた。まるで妻の思い出たちを、衝撃から守るようだった。それを我先にと履き、「わーいあったかい」と喜んでいたあの頃の私を、編み棒で串刺しにしてやりたい。
「編み物って無心になれるやろ。いろいろ忘れられてな、いいもんよな」
姑が頬杖をついてチューハイをあおる。私は、そうだね、と画面に向かって頷いた。うん。よくわかる。彼女が忘れたかったこととは、何だったのだろう。どんな思いで、ずっと編んできたのだろう。夫は亡くなり、子どもたちは巣立ち、誰かに編むこともなくなったとき、何を感じただろう。彼女が缶をテーブルに置いた。コンッと空っぽの音がきこえた。
「俺も飲むわ。もう一本つきあってよ」
私はノンアルコール・ビールを開け、実は編み物を始めたんだと打ち明けた。最初に編んだマフラーは娘には大きすぎた。今はニット帽を編んでいる。冬までには妻にレッグウォーマーを編むつもり。などなど。その日学校であったことを、親に報告する子ども。私はそれに似ていたかもしれない。彼女は減らず口を挟みながら、飽きずに聞いてくれた。いつしか空缶がずらりと並び、娘も寝室に引っ込んでいた。
家族のために編む幸せを、かつて知っていた姑と、知ったばかりの私。親子の会話を始めるのに、15年もかかってしまった。彼女がこの先どれくらい生きてくれるか、分からない。ただ、糸玉をまだまだ残しながら、命の糸が突然ちぎれてしまった人を、私は何人も知っている。かすかな焦り。そして心細さまで覚えたのは、長らく両親のいない私にとって、意外な心の揺れだった。
「俺いま、会社休んでるからさ。その間になんか編むものある?」
口が勝手に動いた。長年の遅れを、隔たりを、今のうちに、埋められるだけ。たとえば、あの日の靴下のように。
彼女はグッと画面に顔を寄せて、答えた。
「あたしゃ現金のほうがええわ」
・・・。やっぱりね。そうでした。そういう人でした。表情が一気に消えたであろう私にお構いなく、ほな寝るわ、の声とともにモニターが真っ暗になった。名残も余韻もない通話オフ。ほんの一瞬でも、彼女と通じた気になった自分のオメデタさに、私はビールの残りを飲み干した。
口ではそう言いながら、小遣いどころかファミレスすら奢らせてくれない彼女だった。年金生活がそれほど大船に乗ったものだとは思えない。近いうちに、せめて腹巻きでも送りつけてやろうか。イニシャルをドーンと入れたダッサイやつを。
婿姑問題は、続く。

ニット帽を編む筆者。2回失敗して編み直し。3度目でようやく完成が見えた
すでに登録済みの方は こちら